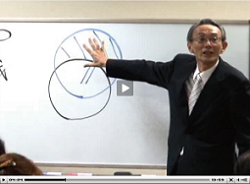発達障害と診断される不登校
発達障害が原因となり不登校となる子がいます。広汎性発達障害やLD、ADHDなどの軽度発達障害、自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群などがあります。病院で検査をすると「グレーゾーン」だと診断される不登校の子も多くいるのは事実です。発達障害と診断された不登校の子への正しい対応についてお教えします。
「発達障害は親の育て方に原因がある」と考えている人がいます。しかし、私たちが今までに1万以上の不登校の家族を見てきましたが、発達障害だと診断された保護者の子育てに問題があるとは思いません。親が原因ではありません。先天的な要素が非常に強いと言う精神科医などの研究がほとんどです。不登校と発達障害の関係についてみていきたいと思います。
発達障害のタイプ
発達障害には様々なタイプがあります。それぞれの障害には特徴があり、子どもの能力や才能も異なっています。障害を持っていても、社会で活躍している大人はたくさんいます。政治家やビジネスマン、映画監督、芸術家などでも発達障害だと診断されながら社会で自立している人が世界中に居ます。それぞれの特徴を掴みながら、子育てをしていきましょう。
発達障害と不登校
最初に、私たちが出会ってきた不登校の中で「軽度発達障害」と診断される子がいました。不登校で精神状態が不安定になると異常な行動をすることがあります。それが発達障害のグレーゾーンだと診断される子もいました。不登校克服後に、他の病院で改めて検査してもらうと、発達障害ではなかった子がいます。もちろん、出会った時から発達障害だとわかる不登校の子もいました。私たちの学校では寮生活をしているので、管理・安全上、発達障害の子は受け入れていません。専門の教育機関に相談して下さい。また、詳しくは『不登校と病気の密接な関係とは?』でも解説しています。
①広汎性発達障害 (PDD)・軽度発達障害
広汎性発達障害 (PDD)の一種で、社会性やコミュニケーションの発達が十分でない状態であることを指す。PDD(pervasive developmental disorders)は①広汎性発達障害(特定不能型)、②自閉症(Autism)、③アスペルガー症候群、④レット症候群、⑤小児期崩壊性障害 (CDD)の5つに分かれます。
言語発達障害~コミュニケーション
他人とのコミュニケーションが苦手で、会話が成り立たなかったりしてしまいます。相手の感情を共有しにくいため、会話の裏にあるニュアンスを把握できません。
社会性障害~対人関係
感情が理解しにくいために、自分の考えを優先してしまうため、周りとの関係が続かなくなります。悲しみや嬉しさなどの感情は持っているのですが、相手がどのような感情なのかは把握できないことがあります。そのため、相手を無視した行動を取ってしまう事があります。
想像障害~イマジネーション、興味の偏向
社会生活での想像力に乏しいと言われています。一方で、興味を持った対象には深くまで関わろうとします。興味のある分野について記憶する事には長けています。周りにとっては理解がしにくいルールに強く固執する傾向もあります。
子どもでは、体育や図画工作分野が苦手な傾向があります。身体の各箇所を同時に動かすことが苦手である。敏感な感覚があるので、音や味に対して強い反応を示します。それが想像によるものなのか、実際に沿う聞こえるのかはわかっていません。
接した方のアドバイス
PDDの子どもは、周りの人の気持ちを理解したり、察知する、暗にわかることが苦手です。そのため相手の気持ちを無視した言動をとることもありますが、悪気はありません。そのため、理路整然と説教をしたり、理解を促したりすることを伝えても効果はありません。「こうしたほうがいいよ。」と取るべき行動を伝えたほうが効果的です。曖昧で、微妙な表現では伝わらないので、注意が必要です。
冗談やからかいも、自分に言われていることだと理解できないこともあります。一方で人に言われている事が、自分にだけ言われていると勘違いする事もあります。一方的に話し続けて止まらなくなることもあります。
場の空気を読めない事があります。また、会話相手との距離感が取れないので、「近い」と感じさせてしまいます。苦手な科目は全く頭に入りません。無理に勉強をさせるよりも、興味が持てる、好きになるようなアプローチを取ると良いです。
この障害を持つ家庭には、大らかで包み込んで子どもを受け入れる態度が求められます。何かを求めたり、急いだり、焦ったりすることでは何も変化は起きません。子どもの特徴と得意な分野を理解して、得意な分野を活かせる環境を用意してあげましょう。
②注意欠陥・多動性障害(ADHD)
③学習障害(LD)
この障害はLD(Learning Disorders)と呼ばれ、日常生活において学習部分の問題があります。脳の知的発達に遅れがあるわけではなく、文字が読めない、日本人なら漢字が読めないとなります。あるいは、文字を書いたりすることや、話すことが出来なかったりもします。また、数学の計算になるとできないなど、読む・書く・話す・計算などの、全てではなく、ある分野で困難を伴う障害です。映画監督のスティーブン・スピルバーグもLDだと公表しています。
④自閉症スペクトラム
自閉症は、通常3歳頃までに発症する先天的な脳の機能障害だと言われています。言葉の発達が遅れていたり、 対人関係や社会性の障害があったり、パターン化した行動を持っていたり、強いこだわりを持っていると言われています。一人遊びが多く、同じ事を繰り返し やったりしています。親であろうとも、無理に関わろうとするとパニックになったりします。あるいは自分の想いを言葉にのせることができず、 会話できない子もいます。自閉症は心の病気ではありません。
⑤アスペルガー症候群
知的障害のない自閉症と呼ばれ、コミュニケーションや対人関係に問題を持ち、特定の分野への興味やこだわりが強いです。感情の理解 が難しく、抽象的な表現 や感情を察する事が苦手です。一方で、好きな分野には特別な能力を発揮する傾向にあり、数学の天才や芸術の天才にアスペルガーが多いとされています。
特別支援学級(学校)
特別支援学級は、地域・学校によって、養護学級、心障学級、相談室、学習室、総合学級、個別支援学級、なかよし学級、あすなろ学級、すみれ学級など、さまざまな呼び方があります。それらの学校では発達障害を持つ子どもに対するケアがきちんと行われています。グレーゾーンでない場合は、こういう学級を利用する事も検討された方がいいかもしれません。他には、適応指導教室を利用している方もいます。『適応指導教室を利用して不登校から学校復帰する3ステップ』で解説しています。
軽度発達障害・グレーゾーンの不登校の解決策
現在、軽度発達障害だと診断される大人も増えて来ています。人間関係で苦しんでいる大人もいます。同級生との人間関係のトラブルが一番の原因となっています。担任の先生が中心となってクラス全体で見守ってくれる状態を作り上げる必要があります。
保護者の忍耐強さが重要です。理論や理屈で説得しても理解できない部分もあります。それを大きく包み込んであげる優しさを持つ保護者が不登校を克服されています。
さらに大切な事は、発達障害の子どもが持つ才能・能力を育ててあげる事です。芸術や数学などに能力が見られる子が多いです。これらの方面で様々な活動をさせて、才能を実力に変えてあげる。そうすると自信を持てるようになります。